もし僕が学校の先生になったら
もし僕が学校の先生になったら──。
そんなことをふと思って、ChatGPTとシミュレーションしてみた。
お題は「僕が先生になったら、どんな授業や課題を出すのか?」。
真っ先に浮かんだのは、夏休みの宿題のことだった。
もし僕が担任だったら、こんな宿題を出す。
「自分にとっての夏」を表現してください。
表現の方法は、なんでもいい。
工作が好きなら工作で。
動画編集が得意なら動画で。
音楽や歌でも、文章や詩でもいい。
大事なのは、「自分が一番輝ける方法」で、自分だけの夏を形にすること。
そして、その過程を思いきり楽しむこと。
保護者からの反応は…やや困惑?
この宿題の話を保護者にしたら、最初は「え?何それ?」みたいな反応になると思う。
そりゃそうだ。だって「自分にとっての夏を表現してください」なんて、ふつうの学校の宿題じゃまず聞かない。
説明していくうちに、たぶん質問攻めになるはずだ。
「じゃあ○○はいいんですか?」
「○○はアリですか?」
みたいに、次から次へと。
中には不安そうな顔をする人もいると思う。
「勉強しなくても大丈夫なんですか?」
「受験に影響が出たらどうするんですか?」
それもわかる。
この宿題は、学力を直接上げるためのものじゃないから。
でも僕は、そういう“結果”よりも、子どもが「やりたい!」と思ったことを全力で形にする時間のほうが、ずっと大事だと思ってる。
同僚からの反応は…ちょっとピリッとした空気
この宿題の話を同僚にしたら、たぶん空気が少しピリッとする。
「足並みをそろえたほうがいいんじゃない?」
「どうやって評価するの?」
そんな声が出てくると思う。
そこで僕は、正直にこう答える。
「評価はしないかな」
その瞬間、空気がほんの少しだけ重くなる。
同僚からすれば、評価のない課題なんてありえないし、成績に反映できない宿題は“意味がない”と感じるかもしれない。
でも僕は、点数や順位よりも、子どもたちが「やってみたい」と思ったことを形にしていく時間のほうがずっと価値があると思っている。
管理職からの反応は…もっと強め
同僚とのやりとりで少し空気が重くなったあと、今度は管理職からの反応。
「なすび先生、これは学校全体の方針から外れています」
「もし保護者から苦情が来たら、どうするんです?」
言葉は穏やかでも、その中身はかなり強めだ。
たしかに、学校は“組織”として動いている。
だから、僕みたいに独断で変わった宿題を出すのはリスクが大きい。
でも、僕は保護者や外からの声よりも、目の前の子どもたちの表情や、今しかない瞬間を大事にしたい。
そして、それを守るためなら、方針から外れてでもやる価値があると思ってしまう。
発表会の日(あくまで想像)
もし本当にやったとしたら、発表会の日はこんなふうになるかもしれない。
机の上には色とりどりの作品が並び、絵や写真、音楽や工作まで、さまざまな「夏」が広がっている。
発表の順番が来ると、子どもたちは少し照れながらも、自分の作品を紹介する。
中には、言葉を使わずに演奏だけを始める子もいるだろう。
きっとその場の空気は、やさしくて、あたたかい。
そんな様子を想像すると、僕は思わずこう感じる。
「この瞬間のためにやりたいんだ」
もちろんこれは、あくまで僕の想像の光景。
現実にやるとなれば、きっと違う面も出てくるだろうけど──。
僕が「外からやる」と決めた理由
学校の中で何かを変えようとすれば、どうしても時間がかかる。
足並みをそろえ、根回しをして、会議で承認を得て──。
そのプロセスは大切だし、そこでしかできない変革もあると思う。
でも、その間にも、しんどさの中で毎日を過ごしている子どもたちがいる。
「今」助けを必要としている子に、数年後に届く変化は間に合わない。
僕は、その手を伸ばせるかもしれない少数を見捨てたくない。
そして何より、周りの評価や方針を気にせず、目の前の子どもたちの“今”に全力で向き合いたい。
だから僕は、学校の外からやることを選んだ。
学力を上げることでも、目標を達成させることでもなく、
「自分なりの学び」を見つけていく時間を、一緒につくっていくために。
あの子の“やってみたい”が消える前に
教育を変える方法は、中からも外からもある。
中から変えるには、時間をかけて根回しをして、組織全体で進めていく力がいる。
外から変えるには、制度や枠に縛られない代わりに、孤独や限界とも向き合わなければならない。
どちらが正しいわけでもなく、それぞれにしかできない役割がある。
僕は外からやることを選んだ。
それは、目の前で手を伸ばせる子がいるなら、すぐにその手を握りたいから。
今日の笑顔や、「やってみたい!」という小さな火が消えないうちに受け止めたいから。
数年後じゃなく、今この瞬間に届く支援でありたいから。
いつか、この小さな火が広がって、大きなあかりになる日が来るかもしれない。
その時、「あの時の一歩があったから」と思ってもらえたら、きっとそれで十分だ。
子どもたちの「やってみたい」が消えてしまう前に、その瞬間を守れる活動を続けています。
この記事に共感していただけたら、OFUSEで応援いただけると嬉しいです。
👉 OFUSEはこちら
関連記事
完全訪問型フリースクール”なすび”をもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

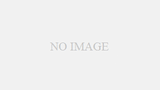

コメント