「教える」って、そんなに偉いこと?
僕は子どもたちと関わるとき、あんまり「教えている」って感覚がない。
もちろん、何かを伝えることはある。
でもそれは、「知らない子に知識を授ける」みたいな偉そうな感じじゃなくて、
「僕が知ってることを、必要そうなときに、ポロッと共有する」くらいのこと。
そもそも「教える=上から」っていう感覚を、僕自身があまり持っていない。
だからこそ、教えることによって上下が生まれる、という発想もあまりピンとこない。
それって、子どもたちとの関係の中で自然にそうなっていったというより、
最初からそうだったんじゃないかと思う。
僕はたぶん、誰に対してもあまり「役割」ってものを背負って関わっていない。
先生でも、子どもでも、校長先生でも、
納得できないことがあれば「それは違うでしょ」って普通に言うし、
その人がどんな肩書きであっても、「人と人」として接している。
だから、支援者として子どもと関わっているときでさえも、
どこかで「支援している」という感覚すら薄いことがある。
そんなふうに話していたある日、
ChatGPTと話していて、ふとこんな言葉が浮かんだ。
―― これは「共創」って言葉が一番しっくりくるかもしれない。
「教える」でも「支援する」でもない。
子どもたちと一緒に、なにかを作っている感覚。
そのまま言葉にするなら、“共に創る”、つまり「共創」だった。
自然学校での「藍染」と「夜の散歩」
自然学校の最終日の前日、僕は子どもたちにこう聞いてみた。
「せっかくみんなで作った藍染のTシャツ、最後にそれを着て帰らない?」
「いいやん!」と盛り上がる子も多かったけれど、
中には「無理無理!」って拒否する子もいた。
ああ、これはもう「全員で着よう」って空気ではだめだ、ってすぐに感じた。
だから僕は言い方を変えた。
「これは強制じゃないよ。着たくない子は、着なくていい。
ただ、これはみんなで作ったものだし、なすびとしては
お父さんお母さんに“楽しかったよ”って伝わる形になればいいなって思っただけなんよ。
どうするかは、任せるね」
この空気を共有できたことで、場は少しやわらかくなった。
結局、多くの子が着ることを選んでくれたけど、無理に着せることはしなかった。
もうひとつ、夜の散歩を提案したときのこと。
「星空観察ができるかもしれないから、夜に散歩してみない?」
「行きたい!」って言う子もいれば、「いや、無理!」って即答する子もいた。
最初、僕は「じゃあ全員で行くか、全員で行かないかをみんなで決めよう」って伝えていた。
でも、多数決にはしたくなかった。
なんでかというと、多数決って「納得していないまま流される人」を生むことがあるから。
実際に話を聞いてみると、行きたい派は
「せっかくの自然学校やし、やれるならやりたい」という声が多かった。
一方で反対派は、「もう疲れてる」「休みたい」という気持ちが大きかった。
どっちの意見も、ちゃんとわかるし、どっちも真っ当だと思った。
だから僕は一度こう伝えた。
「みんなの意見はわかった。じゃあ一旦、先生たちと話し合ってみる。
行きたい人は行って、休みたい人は休むって形にできるか考えるね。
夕食までには伝えられるようにするね。それでいい?」
その後、先生たちと相談して、実際に希望制の散歩になった。
どっちを選んでもOK。
その選択肢があるだけで、子どもたちの空気が変わったように感じた。
最終的には、9割近くの子が参加してくれた。
“やってみたい”という気持ちが自然に動いた結果だったんだと思う。
なぜ多数決がイヤなのか?
僕は、子どもたちとの話し合いの中で「多数決」を使うことがほとんどない。
それは、僕にとって“決め方”ってすごく大事なことだから。
多数決って、一見するとフェアな方法に見える。
でもその裏には、「納得していない人」が必ず生まれるという側面がある。
たとえば、ほんとは行きたくないのに、
「みんな行くから仕方なく行く」
「反対したら空気悪くなるから、黙っとこ」
そんなふうに流されてしまう場面って、子どもでもよくある。
それって、自分の意思じゃなくて“空気”に従ってるだけ。
内心モヤモヤしたまま、ただ合わせているだけの状態って、
本人にとっても辛いし、僕はそれを無視したくなかった。
もちろん、みんなで何かを決めるとき、全員の意見が一致するなんてことはほとんどない。
でもだからこそ、一人ひとりの「納得感」をちゃんと大事にしたい。
どの意見にも理由がある。
その理由に耳を傾けて、できる限りみんなが「これならいいかも」と思える着地点を探したい。
それが、「共創」って言葉の意味でもあるんじゃないかと思う。
「決める」ってどういうこと?
「自分で決める」って、すごく当たり前のようで、実はとても大切なことだと思う。
誰かに決められたことをやるのって、正直しんどい。
「やらされている」とか「しかたなく」という感覚が、どこかにモヤモヤを残す。
だから僕は、子どもたちが「どうしたいか」を自分で選ぶ時間を大切にしている。
たとえば、「行く?」「やってみる?」と聞くだけではなく、
その子が納得できる材料をきちんと提示して、選べる余地をつくる。
いつも正解を出せなくてもいい。
でも、「選んでもいいんだ」ということを知っているかどうかで、
その子のこれからが少しずつ変わっていくと思う。
これからの時代は、正解のないことばかりだし、
「誰かが決めたルールに従っていればいい」という時代でもなくなっていく。
だからこそ、自分で考えて、自分で選ぶ力が必要になる。
そしてそれは、「選んだことを誰かに否定されない」という安心の中でしか育たない。
僕にとって「決める」というのは、
その子が“自分の人生を自分で選んでいい”ということを伝える行為なんだと思う。
共創がもたらす子どもたちの変化
「共創」という関わり方を大事にしていると、
子どもたちの中に、少しずつ変化が生まれてくる。
僕が特に感じるのは、「自分たちの力を信じられるようになる」ということ。
誰かにやらされるのではなく、
自分たちで考えて、選んで、動いた結果として何かができたとき、
それはそのまま「できた!」という実感になる。
「あれ、自分たちで作れた」
「これも、自分たちで決めたんだ」
そんなふうに思える経験が増えていくと、
次に何かに出会ったときにも「もしかしたら、自分たちでできるかもしれない」って感じられるようになる。
それはきっと、自信とか、希望とか、そういう言葉で表されるものかもしれない。
でも僕はそれを、もっとシンプルに、
「その子が“自分”を信じられるようになること」だと思っている。
共創は、何かすごい結果を生むための手段じゃなくて、
その過程の中で「自分って意外とやれるかも」と思える瞬間を育てていく。
それが、僕にとっていちばん大きな意味だと思っている。
共創は子どもだけじゃない──大人とも、保護者とも
「共創」って言うと、どうしても子どもとの関わりをイメージしやすいけれど、
僕にとっては、それは大人との関係の中でも同じように大事にしているものだ。
たとえば、不登校の訪問支援の現場では、
保護者の方と話す時間もすごく大切な時間になる。
「今この子は、こんなことを考えているみたいです」
「なので、こんなふうにアプローチしてみようと思っています」
という話をした上で、
「ご家庭でも、こういうことができそうなら少しやってみてもらえたら…と思うのですが、どうですか?」
というふうに、提案としてやりとりをする。
決して「こうしてください」ではなくて、
「一緒にこの子のことを考えていきませんか?」というスタンス。
相手が親でも先生でも大学生でも関係なく、
僕はなるべくフラットな目線で「どう思う?」と聞く。
そこに立場や経験の差を持ち込むよりも、
それぞれの人が自分の目で見て、感じたことを共有し合える方がいいと思っている。
学校の先生に対しても、僕の知っていることを伝えるときは、
「こういうやり方にはこういうメリットとデメリットがあります」
「別のやり方だと、こんなふうにもなります」
といくつかの選択肢を示した上で、
「先生たちはどう考えますか?」と問いかけるようにしている。
その方が、対話が生まれるからだ。
そして、対話の中からこそ、“その子に合った選択”が生まれてくると思う。
自然学校でも、不登校支援でも、関わり方の本質はいつも変わらない。
「この子にとってどう在れるか」を、一緒に考えること。
その姿勢こそが、共創だと思っている。
共創のむずかしさと、それでも大事にしたいこと
共創って、いつもうまくいくわけじゃない。
話し合いをしても、誰も何も言わなかったり、
逆に意見が真っ二つに割れて、どうしたらいいか迷うこともある。
でも僕は、そういう場面こそ大切にしたいと思っている。
たとえば、誰からも意見が出ないとき。
そんなときは「何も言わない=納得してるってことでいい?」と一度だけ確認して、
そのまま進めることもある。
無理に意見を引き出そうとはしない。
代わりに、「あとからでもいいから、何かあれば教えてね」と余白だけは残しておく。
逆に、意見が強く割れるときは、それぞれの声をちゃんと聴く。
「反対って言ってたけど、どんな理由があるの?」
そうやって丁寧に聞いていくと、どの意見にもちゃんと背景があることがわかる。
多数決でさっと決めてしまえば、場の収まりはいいかもしれない。
でも、そこに「誰かが置いていかれる」感覚が残るなら、僕は避けたい。
共創には手間も時間もかかる。
でもその分、一人ひとりが「自分の声が届いた」と感じられる。
そして、それが信頼や納得感につながっていく。
多少のもどかしさがあっても、僕はやっぱりこのやり方が好きだ。
「この関係の中でなら、自分を出していい」と思ってもらえること。
それが共創の一番の力だと思う。
共創は在り方そのもの
「教える」でもなく、「支援する」でもない。
僕が子どもたちと関わるときに大切にしているのは、
一緒に考えて、一緒につくっていくという感覚だ。
それはただの関わり方や技法ではなく、
僕自身がどう在りたいか、という“在り方”そのものでもある。
誰かに何かを伝えるときも、
立場や年齢や経験の差を理由に、上から関わることはしたくない。
子どもにも、大人にも、保護者にも、先生にも、
できるだけフラットな目線で、一人の人として向き合いたい。
それが自然なことでありたいし、
僕にとっては、それ以外の関わり方の方がよほど不自然に感じる。
肩書きが何であっても、相手が誰であっても、
僕はきっと変わらない。
たとえ相手が校長先生でも、教頭先生でも、
「それは違うと思います」と普通に伝えることができる。
そのとき、自分を大きく見せようともしないし、相手を下げようとも思わない。
ただ、その人と、その場に、まっすぐでいたいだけだ。
「共創」は、そんなふうに人と関わっていく中で、自然と生まれてくるものだと思っている。
特別なことをしているわけじゃない。
でも、こういう在り方の先にこそ、
本当に意味のある関係や変化が育っていくと信じている。
子どもたちと「共に創る」関係を、これからも大切にしていきたいと思っています。
もし僕の想いや活動に共感していただけたら、OFUSEでの応援が励みになります。
👉 OFUSEはこちら
完全訪問型フリースクール”なすび”をもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


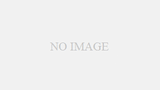
コメント